誰に投票すればいいのかがわかるシリーズ番外編
公開日:
:
ブログ
投票率の低さは全国的な問題ですが、それを議論するときに出る話と言ったら、やれ「投票所を増やせ」とか「駅や市街地に出張所を出せ」、あるいは「投票バスを出せ」といった投票機会の拡充案が多いのが現状です。
そうすると、これに対して出てくるのが「いや、そもそも自分の権利を自覚させないと意味ない。」といった有権者教育論も出てきます。
今回の県議会議員選挙は、告示を見てみるとなんと14選挙区のうち10選挙区が無投票ということになっています。当然過去最多です。
無投票の理由としては新人、女性の立候補者をはじめ「議員のなり手不足」が顕著なこと。これが問題のない地域ならむしろ選挙費用もかからないので理想的なのだけど、問題のない地域などある訳ないので、これはつまり「無関心」のなせる業だろうと思います。低投票率自体、「無関心」の証明であって、なんでこんなことになるんでしょう?
かつては高い投票率の選挙だってありました。高い時と低い時を比べてみて見えてくるのは、候補者の数と顔ぶれに左右されていることです。もちろん、喫緊の問題が大きい場合もそうです。
それだって結局「無関心」を証明してしまっているわけですが、要は「議員が政治を変えることに信憑性がない」、ということに尽きるわけです。

つまり、投票に行かなかったからといって「政治に自分の一票が反映されないのに、投票したって意味ないじゃん」てことになっているわけです。「投票率が高くなったから、だから何が変わるの?」って思われてしまっているんだろうということです。
これをひっくり返そうと思ったら、たとえば新人が当選1期目で何かとてつもない「大改革」でも起さない限り無理なんじゃないか、と思うわけです。
ではそんなことが可能なのか?ほとんどの場合可能性は限りなくゼロに近いでしょう。特に宮崎県のような保守王国ではなおさらです。
今回の選挙では、テーマとして人口減少、南海トラフ巨大地震、鳥インフルエンザなどの防疫、火山への危機対応、などが挙げられています。
まぁこれもマスコミが煽っている部分もあって、「無難なテーマ」にしといた方が保守を維持しやすいってのもあります。たとえばTPPや集団的自衛権、原発などをテーマにしてしまうと改革派に分が出てしまいかねないからです。
つまり選挙のだいぶ前から、選挙への関心を削いでおくためにマスコミはもちろん、大多数を占める保守層によって情報が操作されている、とも言えるでしょう。
しかし有権者にも非はあって、仮に投票率が高くなったとしても、保守的に飼いならされた市民は、その結果を左右するほどの意識の高さを持ち合わせていないので、ますます「無意味」感が出てきてしまうわけです。

やはり、「立ち上がる」しかないのだと思います。超党派で有志が集まり、議論を始めるべきだと思います。
僕もこれまで市民活動には積極的に関わってきましたが、正直「ちまちま感」にかなり違和感を感じていました。近く、そういう会を立ち上げたいと考えています。おって記事を書いていきます。
関連記事
-
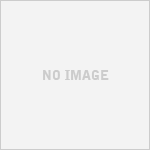
-
本当は怖い節分・・・・
節分。行事の事だと思っている人が多いけど、実際は各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)
-
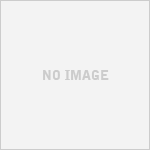
-
もはや愛煙家は非国民?
もはや普通の喫茶店でも愛煙家は外に追いやられる時代になってきたすな。 こないだ見た「不都合な真
-
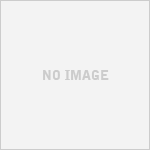
-
交通安全協会費はいらない!
皆さん免許更新の時に、「更新料と協会料で○○円です」って言われて、ごく自然に支払ってま
-
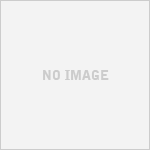
-
■5W1H何と読む?
いやぁ言ってみるもんですねぇ。早速わいおい事務局からメツセージいただきまして、善処して
-
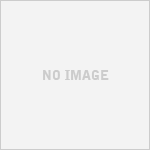
-
北朝鮮に貢献してます。
ボクの弟は都心でパチンコ店を数店マネージメントをしているいわゆる仕掛け人なのだが、パチ
- PREV
- 誰に投票すればいいのかがわかるシリーズ3
- NEXT
- 【悲報】いろいろ責められた件/タウンマネージャー

