作詞の難しさについて書いてみた。
公開日:
:
ブログ, ミュージック・レポート
これまで「泣いた曲」というのは数曲しかない。
ちなみにいくつか書くと、UFOの「DoctorDoctor」、ZEPの「天国への階段」、長渕剛の「祈り」、太田裕美の「木綿のハンカチーフ」、ジョージウインストンの「Longing/Love」など・・・。
「Longing/Love」もだけど、この「Into the Arena/Michael Schenker Group」は例外中の例外。なんでかというとインストだから歌詞がない。つまり純粋に曲の構成、メロディだけで泣けた曲。しかもバラードではない。もちろんマイケルが孤高の存在で様々な逸話があって、そのバックグラウンドが僕のイメージングに影響しただろうし、マーシャルにCryBabyだけという潔さとか、白黒のフライングVを股に挟んだりとか、そういうことも加味されているのかも知れない。あれから36年、泣かせてくれる曲にはなかなか出会えない。
なぜ近年はそういう曲に出会えなくなったのかを考えてみた。まずパターンとして純粋に曲の構成や主旋律からイメージして泣ける場合と、歌詞を聞いてその世界観や自分に準えて泣ける場合がほとんどだろうと思う。
後者の場合は例えば洋楽だと歌詞の意味がわからないから、たとえそれがいかにゲスな詩だったにしても関係なかったりする。そういう意味では邦楽は不利だ。歌詞が優れていないとせっかくいい曲も感動できなかったりするかも知れない。
邦楽の場合、たとえば民謡や童謡等を除けば、その8割以上はラブソングであって、つまり「あなた(あの人)と私」という設定の恋愛がテーマだ。もちろん三角関係だの色々と例外もあるだろうがここでは無視する。
そうすると、色々な「愛のかたち」が歌詞にかかれているわけだけど、曲は何万曲あっても、「愛のかたち」のパターンはそれほど多くない。純愛、片思い、略奪愛、不倫・・・
もちろん、それぞれの具体的な表現は様々だから、一見「違う詩」に見えても、曲をたくさん知っている人から見れば、「あぁそーゆーのいろんな人が歌ってるよ」ってことになって、新鮮味はない。
たとえばミスチル世代に聞くと、泣ける曲は「OVER」だという人が多い。もちろんボクも知っている曲だが、あらためて詩を読むと、相手の女性が自分からどんどん心が離れていってしまい、今では思い出と化した、という、まさに思春期の若者の心をくすぐる内容だ。「木綿のハンカチーフ」にも通ずる。
表現こそ違え、同様のテーマは何度となく歌われてきているが、それはそれ。その世代その世代にとってのアンセムとなっていくわけだけど、古い世代がそれに泣ける可能性は低い。
だから作るほうも大変だ。もっとも、同世代しか対象にしてないよ、と言われればそこまでだけどね。
したがって、今後泣ける曲と出会えるとすればやはりメロディ、またはそれを含めたアレンジ、ということになるのだろう。
とはいえ、「泣ける曲」ばかりである必要もなく、癒される、楽しくなる、興奮する、など、曲の役割はいろいろあっていいわけだから、新しい曲には期待していきたい。
最近では、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」などはかなり秀逸だと思うし、「アナと雪の女王」の「レット・イット・ゴー」はなかなか素晴らしいし、気に入っている。
ちょっと脱線するけども、この「レット・イット・ゴー」は多言語バージョンで25カ国それぞれの歌い手さんが歌ってて、これ見て思ったのは、とにかく全員感動できるレベルの歌唱力で、シロウトのそれと比べるとやはりうまい人はうまい!一時期、松たかことMayJでどっちがどうだみたいな話があったけど、ぶっちゃけ言うとどっちもいいし、あえて優劣を付ける必要なんてどこにもない。
さてそんなボクも詩を書かなくなってから久しい。理由は前述したようにラブソングは書けるパターンが存在しない。マテリアルを変えればいくらでも書ける、と思われるかも知れないが、それは書く側にとっては「やっつけ仕事」でしかない。
だからラブソングではなく、現代における(ここが大事)人生観や、不条理、戒めや希望、そういったものでないと書けなくなっているのだ(仕事として依頼されたら別だけど)。
問題は、そういう類の詩はまず間違いなく「暗い」。だからマイナーコード多用となる。
もうひとつ、「詩」というのは「文学」であって、音楽の一部ではない。曲に乗せるという前提があると難易度が高くなり、文学性が損なわれかねない。もちろん韻を踏んだり擬人化などで、たまたまいいアイデアが浮かんだりすることはある。
メロディやリフについても車の中や寝る前に閃くことも多々ある。特に寝る前に閃いてそのまま寝てしまったにも関らず覚えている曲などはやはり「閃くべくして閃いた」と言える。
そんなストックを相当溜め込んでいるのだけど、じゃあその断片たちを結集して新曲を作り、それをどうしていくのか、ここがまた厄介なテーマなのだ。
ボクはプロではないしプロ志向でもない。だから作品を世に発表し聴いてもらい作り手として認知してもらい次回作へ繋げる、というルーティンは、極端に狭い範囲でしかできない。これを広くやろうと思ったらプロになるか、プロ志向になるしかない。必然的に生活そのものの、いや人生の考え方を変える必要がある。つまり家庭や仕事を犠牲にする覚悟が必要なのだ。正直そんな度胸はないし、他にやるこたたくさんある。
だからオリジナルを作るのは気が進まないし、できても発表する気にもなれない、いまのところ。
それに、そもそもオリジナルである必要は現代では極めて希薄だ。プロのアーティストでさえもそうであるように、過去の名曲を自分の理解で表現する、俗に言う「カバー」というのがかなり主流になっている。
リズムを変えたり調子を変えたり、あるいはジャンルごと変えてしまったり、つまりアレンジ力の品評会さながらの時代になっている。これはこれで楽しいし、音楽の楽しみ方としてかなりの比率になってきていると思う。場合によっては「アンサーソング」的なものや、モチーフと宣言してオリジナルを作るケースだってある(もっともこれは60年代からあるけど)。
そんなわけで僕の新作が出るのは、まだ随分先になりそうです。生きてれば・・・。
関連記事
-
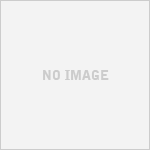
-
直ちに人体に影響の出るレベルではない・・・かなぁ?
あぁあ~、まーだ迷ってんのねぇ、政府も東電も。廃炉がそんなに惜しいか! なぜ本当のこと言わないのか
-
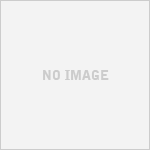
-
見返りのないもの、それが・・・
昨日の記事には予想外に反響いただき、紹介したことが間違いでなかったと確信しました。 今、オレゴ
-
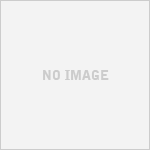
-
地域ブログは何ができる?
唐突で申し訳ないんすがね、せっかくオフ会などで交流も生まれ始めてますし、ちびっと提案あるす。
- PREV
- ひょんなことからコンビニ比較
- NEXT
- 参院選、行くか!

