公務員の異動制度はデメリットしかない理由
公開日:
:
最終更新日:2014/04/05
ブログ
役所にはそれほど行くほうではないのですが、たまに行くと担当がしょっちゅう替わっていることに気づきますよね。言うまでもなく「異動」があるからにほかならないのですが、市民からすれば何のメリットもないような気がします。
そもそも、なぜ「異動」はあるのでしょうか?
まず、「組織内の年齢的・地位的アンバランスを解消するため」というのが考えられますね。ただ、これだけではこれほど頻繁に行われる必要性は考えにくいと思われます。
次に「作業や業務のマンネリ化・後進育成の停滞・取引先との癒着・権限の私的流用といった問題を予防・回避するため」というのもあるでしょう。しかしこれは、自ら監視体制の甘さを暴露しているようなものであり、理由とはいいがたいでしょう。それに「対外的」に「体裁作り」という感も否めないし、ですね。「庁内Gメン」とか置けばよくね?

もうひとつは「業務が肉体面・精神面において極端にハードである場合、数年単位で人を入れ替える必要があるため」というのもあるでしょう。ただ、これは自己申請で「異動願い」や「調停」等の処理をすればいい話なので、これも理由とは言いがたいと思われます。
つまりたいした理由など無いな、と思うわけです。
一方で「オールラウンドな経験・実務の蓄積のため、責任を持って判断できるよういろいろな仕事を経験させ、多方面から思考できる人材を育成する必要があるため」、という声も聞きます。
しかしこれも少しおかしい気がします。というのは(ボク自身「元公務員」ですが)、試験はいわゆる学力考査が主で、これに多少の作文・面接が加わる程度で、「能力」という観点はないわけです。例えばリスクヘッジや判断力、柔和な創造力、臨機応変な応用力など、現場で「生きる」能力を考査することはほとんどありません。したがって、より高い人材育成をするのであれば採用の時点から「能力主義」を取るべきであり、学力や教養に偏るとスペシャリストもゼネラリストもたいして育たない、と思われるのです。

さて、そんな状態なのでどの部署に行っても「スペシャリスト」がいません。新しく着任した仕事を理解、体得するのに1年かけ、慣れだした2年目に新規施策や施策改善を構想してもその頃には異動、なんてことがザラ。当然、「前例」にのっとって業務に当たらざるを得ないので革新的なアイデアやコストダウンも発想できないし、したとしても慣例に飲み込まれてしまうという悪循環しかないわけです。
思い切って定期的な異動という考え方をやめれば、「人事課」という課自体の人数も大幅に減らせる気がします。そうすれば「人事課」の仕事は主に「異動願い」の受付・審査、各課のバランス取り、調停、能力査定、そして「監視」、くらいになるのではないか、と思うわけです。名刺や名札、作業服のネーム等の作り変えも随分減るでしょうし、なによりスペシャリストが育成できるはずです。
まず1~2年程度は希望部署か、それに準ずる部署に配属させ、その後スペシャリストを目指したい人は希望を出し、配置転換なり残留なりを決め、その後も基本的には個人の能力を発揮できそうな部署への配属希望を優先させる流れの方が、モチベーション的にも違うのではないか、と思うのです。
また、各課の長は欲しい人材を交換できるような、プロ野球で言う「トレード」などを可能にし、より強固な部署作りをするようにしたらどうか、とも思いますが、これはその部署の「長」がそれだけ自分の部署に対して責任と愛をもっている必要があるでしょうし、そもそも「長」が異動を繰り返していたら元も子もないですけどね。
ところで、実際の職員をモデルに起用した奈良県生駒市の職員採用試験ポスターがかなり話題になっています。もうほぼトリプルA。すぐにでも戦隊が組めそうです。都城市にはとうていできそうにないですが、ね。

関連記事
-
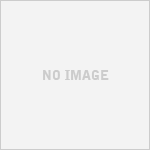
-
欲しすぎるぅ!欲すぃ~これ!
http://www.youtube.com/watch?v=XNaULIQ1uF8[/youtub
-
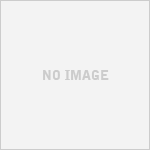
-
■何も知らないのは国民だけ?
はるさんに頂いたコメントにあったように、「マニフェストを知らずに、あるいは知っててもそれがどういう
-
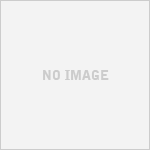
-
2003/10/19
「経惟」「雅功」このたぐいの名前を迷いなく読める人はどれくらいいるのだろうか。ちなみに「荒木経惟」と

